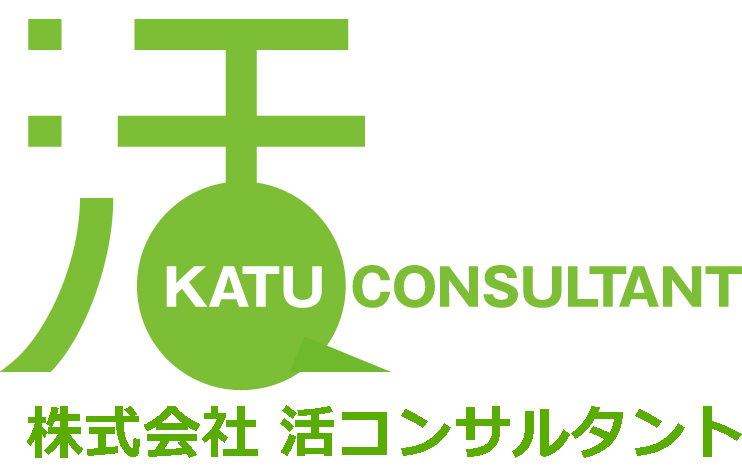トヨタ生産方式における二本の柱(1)
ニンベンのついた自働化
トヨタの管理のヒントはカウボーイ?
トヨタ生産方式2本の柱の1つ。
「ニンベンのついた自働化」をご紹介します。
私が、前々職の(社)中部産業連盟に在職していたときに
先輩から、
「トヨタの管理のヒントはカウボーイにある。わかるか。」
と言われました。
「わかりません。」
けれども結局問いかけだけで、何も教えてくれませんでした。
ケチ!
と言いたいところですが、当時はそんなもの。
簡単に教えてもらったことは身につきませんが、
自分で悩んでわかったことは忘れません。
教えない教育というのが良かった時代です。
そしてやっとわかったこと。
あとからご紹介します。
異常に気づく機械の進化と効率化
30年前の機械は、異常が起こっても停まりませんでした。
異常とは、完全におかしくなる前の予兆のようなものです。
たとえば、
・エア圧が足りなくなった
・温度が上がり過ぎている
・品物の流れが悪い など
異常があっても機械が停まらないと、ずっと不良を造り続けたり
機械が壊れたりしてしまいます。
そこで人が見張っていないといけない。
異常に対応するために人が機械1台に1人ついて常に監視する必要があり、
機械の台数だけ人が必要でした。
これでは、まったく人の効率が良くありません。
そこで異常が起こったら、機械が自ら停止する機能がつけられました。
これをニンベンのついた「自働化」と呼びます。
機械に人の知恵を付けるという意味です。
今の機械には、異常停止装置がついています。
異常があると、機械が自働停止して、赤ランプが点いて、
ブザーやメロディが鳴ってオペレータに知らせてくれます。
ニンベンのついた自働化ができて、
人が、機械を監視する作業から解放されました。
異常時だけ機械を診る作業になって
1人で何台もの機械を受け持つことが可能になりました。
品質管理とマネジメントのバランス
この考え方はマネジメントに応用できます。
異常を中心に診ることにより、
少ない人で多くの機械、現場や人などを受け持つことができます。
異常とは不良になる前の予兆です。
品質管理では、(工程が安定していれば)
規格はずれになる前に基準線が引かれます。
そして基準線を越えた時(異常)にアクションをとります。
(その他にも異常の定義がありますが)
異常時すみやかにアクションをとることで
規格はずれなどの不良発生を未然に防止することができます。

また、基準内で、適度なバラつきで変動している(正常)時には
何もする必要ないので効率も良いのです。
というより、
正常なバラつきで値がおさまっている時に
すべて中心値に合わせようと調整し過ぎると、
逆に結果が安定しなくなります。
人は、少しでもズレているのを直そうと
つい、いじりたくなりますが。
ちょうど、せっかく社員が自主性を発揮してうまくいっているところに
わかっていない管理職があれこれ口出しして
(まっすぐ走らせ過ぎようとして)
おかしくしてしまうことがあるのと同じ。
カウボーイ式管理の極意
さて、冒頭にご紹介した
カウボーイのやっている牛の管理
(トヨタ生産方式における管理の要諦のひとつ)は
「ニンベンのついた自働化」と同じです。

カウボーイは牛の1頭、1頭を見ているわけではないそうです。
何もしないで牛の群れにくっついているだけです。
牛の群れがコースをはずれそうになったら、先頭に行って軌道修正する。
あるいは、何頭かの牛が群れからはみ出したら
行って牛をポンポン叩いて、群れに戻す。
すなわち、正常時は何もしない。
異常時にすみやかにアクションをとる。
これが、管理の要諦なのです。
管理を行うためには、正常と異常の区分けをしなければならない。
それが3S(整理・整頓・清掃)であり、標準化 です。